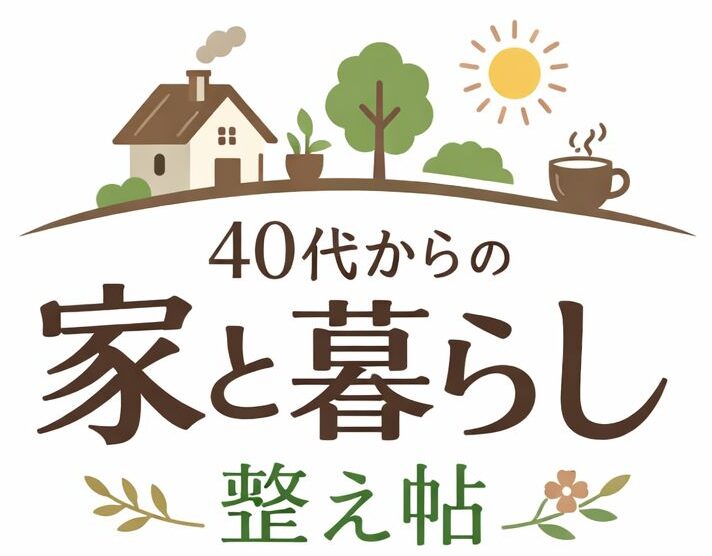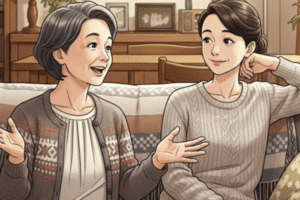「昔から 親と同居 しているから、家事は言わなくても分かってるはず…」
もしあなたがそう感じているなら、それは危険信号かもしれません。長年同居している親子だからこそ、家事分担 がなんとなく「固定化」し、不満が心の中に溜まり続けているケースは少なくありません。
「この家事はいつも私の仕事…」
「もういい年なのに、いつまで親に甘えてるんだろう…」
そんなふうに感じてしまうのは、ごく自然なことです。しかし、家事分担は親子の関係を悪化させるものではありません。むしろ、お互いを尊重し、ストレスなく暮らすための大切なコミュニケーションツールです。
この記事では、昔から親と同居しているあなたに向けて、家事の不満を解消するための3つのモデルケースを紹介します。これを読めば、凝り固まった家事の役割を見直し、心が満たされる親と同居 生活がきっと見つかるはずです。
第1章:親と同居 だからこそ悩む 家事分担 の根本原因
同居歴が長い親子が抱える 家事 の悩みは、一言で「やらない」ことだけではありません。実は、以下の3つの根本原因が隠れています。
1.1 「 家事 の役割」の固定化と「甘え」の構造
長年一緒に暮らしていると、家事 の役割がいつの間にか固定化されてしまいます。例えば、料理は母親、ゴミ出しは父親、部屋の掃除はあなたの役割…といった具合です。この「なんとなくの分担」は楽な反面、不満が言いにくい「甘えの構造」を生み出します。
1.2 「言わなくても分かる」というコミュニケーションの欠如
親子だからこそ、「言わなくても分かってくれるだろう」という期待が先行し、具体的な不満を口に出せなくなることがあります。「お母さん、そのやり方だとカビが生えるよ」といった率直な意見を言えず、小さな不満が心の中に積もり積もってしまいます。
1.3 変化する「ライフスタイル」とのギャップ
昔は通用した家事のやり方や分担が、親の年齢やあなたの仕事、ライフスタイルの変化によって合わなくなってきています。親の体力が落ちたり、あなたの仕事が忙しくなったりしても、古い 家事分担 がそのままになっていることが、現在のストレスにつながっているのです。
これらの問題を解決するには、一度立ち止まって、家事の役割を客観的に見直すことが不可欠です。

第2章:親子関係で選ぶ!家事分担 モデルケース3選
ここでは、昔からの親子関係を尊重しつつ、家事 の不満を解消するための3つのモデルケースを紹介します。あなたの家庭に最適な方法を見つけてください。
モデルケース1:役割を再設定する「完全分担型」
こんな親子におすすめ:
- 自分の時間やプライベートを重視したい人
- 家事のやり方や頻度について、自分の基準を保ちたい人
- 過去の役割分担をリセットしたい人
このモデルは、家事の項目ごとに「誰がどの家事の責任を負うか」を再定義するものです。これまでの「なんとなく」の分担を捨て、紙に書き出して明確にすることで、言いにくかった不満を解消できます。
| 家事項目 | 親の担当例 | 子(あなた)の担当例 |
|---|---|---|
| 料理 | 晩ごはんの調理 | 朝ごはん・昼ごはんの調理、外食・中食の手配 |
| 掃除 | リビングや共有スペース | 個人の部屋、水回り(キッチン、風呂) |
| ゴミ出し | 生ゴミ | 資源ゴミ、不燃ゴミ(力仕事) |
| 買い物 | 食材・日用品(近所) | 重いものの買い出し(車で) |
メリット:
- 自分のペースで家事に取り組めるため、ストレスが少ない。
- 責任が明確なので、「誰がやるべきか」で揉めることがない。
- 親への「甘え」の構造を断ち切り、自立した関係を築ける。
デメリット:
- 分担を明確にすることで、最初は親が戸惑うことがある。
- 家族の協調性が失われると感じる場合がある。
モデルケース2:得意な家事をシェアする「共同協力型」
こんな親子におすすめ:
- 昔から家族の協力体制が強い家庭
- 家事を通じて親子の会話を増やしたい人
- 家事を完全に分けることに抵抗がある人
このモデルは、家事 項目ごとに「得意なこと」「好きなこと」を話し合い、協力し合う方法です。「役割分担」というよりは「協力体制」に近いため、感謝の気持ちが生まれやすいのが特徴です。
- 料理が得意な親がメインで調理する。あなたは後片付けや洗い物を担当し、親の負担を軽減する。
- あなたは力仕事が必要な買い出しや重いゴミ出しを担当する。親は部屋の整理整頓や簡単な掃除を担当する。
- お互いのスケジュールに合わせて、週末に一緒に大掃除をする。
メリット:
- 親子の共同作業が増え、コミュニケーションが活発になる。
- お互いの得意分野を活かせるため、効率が良い。
- 感謝の気持ちを伝えやすく、関係がより円満になる。
デメリット:
- 担当が固定されていないため、「結局、私がやることになった…」と不満が生まれる可能性がある。
- 共同で使う**水回りやキッチン**は特にルールが必要になります。
👉詳細は40代「親と同居」で揉めない!水回り・キッチンの共有ルールとリフォーム戦略でご確認ください。

モデルケース3:役割を固定しない「柔軟対応型」
こんな親子におすすめ:
- 仕事のシフトが不規則で、家事を決まった時間にできない人
- ルールを厳密に決めるのが苦手な人
- 体調や気分に合わせて家事のペースを調整したい人
このモデルは、家事担当や責任を固定せず、「気づいた人がやる」という、最も自由度の高い方法です。ただし、お互いの家事に対する意識が高いことが前提となります。
- 基本的に、自分のことは自分で行う(洗濯、部屋の掃除など)。
- 共有スペースは、「汚れていることに気づいた人」が掃除をする。
- 料理は、「今日は私が作るよ」と声をかけ、作れない日は各自で済ませる。
メリット:
- ルールに縛られず、臨機応変に対応できる。
- お互いに感謝の気持ちが生まれやすく、関係が良好になる。
- 家事の負担が体調やスケジュールに左右されにくく、ストレスが少ない。
デメリット:
- 「私ばかりやっている気がする…」という不満が生まれやすい。
- お互いに「やってもらえるだろう」と期待しすぎると、家事が滞ったりする。

第3章:家事分担 を成功させるための具体的なルールとヒント
家事分担 モデルを選んだら、さらに一歩踏み込んで、具体的なルールやヒントを実践しましょう。
3.1 成功の鍵は「見える化」と「感謝」
- 家事を「見える化」する: 家事分担表を冷蔵庫に貼る、またはLINEグループで共有するなど、お互いの役割を可視化します。これにより、「誰が何をするのか」が明確になり、責任感が生まれます。
- 「ありがとう」を言葉にする:家事をやってもらうのは当たり前ではありません。「ありがとう」「助かったよ」といった感謝の言葉を意識して伝えることで、お互いのモチベーションが維持されます。
3.2 曖昧な表現をなくす「具体的ルール」の例
「掃除」や「片付け」は、人によって基準が異なります。そこで、具体的な行動レベルでルールを決めます。
| 曖昧なルール | 具体的なルール |
|---|---|
| 掃除は私がするね | リビングの掃除機がけと、水回り(お風呂・トイレ)の掃除を私が担当するね |
| 洗い物は適当に | 食事後の洗い物は、シンクに溜めずにその日のうちに済ませようね |
| 洗濯は私に任せて | 洗濯は毎日午後、私がまとめてするね。週末は各自でしてね |
親との円満な話し合いの進め方や、お金に関するルールについては、参考記事:「親と同居 メリットと家計管理のコツ「お金の不安をなくす方法」で詳しく解説しています

3.3 介護も見据えた家事分担の話し合い
今は家事の分担ができても、将来、親の介護が始まったとき、家事の負担は大きく変わります。
- 元気なうちに「もしものとき」の家事分担について話し合っておきましょう。
- 介護サービス(家事代行など)の利用も視野に入れ、一人で抱え込まない体制を築いておくことが大切です。
- 介護保険制度や家事代行サービスについては、厚生労働省のウェブサイトなど公的な情報を調べておくと安心です。【外部リンク】厚生労働省:介護保険制度
まとめ:家事分担 は「最高の親孝行」
親との家事分担は、単なるタスクの割り振りではありません。それは、長年家族のために頑張ってくれた親の負担を軽減し、自分のことも大切にするための、最高の親孝行です。
この記事で紹介した3つのモデルケースを参考に、親と話し合ってみてください。家事の分担ルールを定めることで、お互いの暮らしがより豊かで、心が満たされるものになるはずです。
🌸関連記事🌸