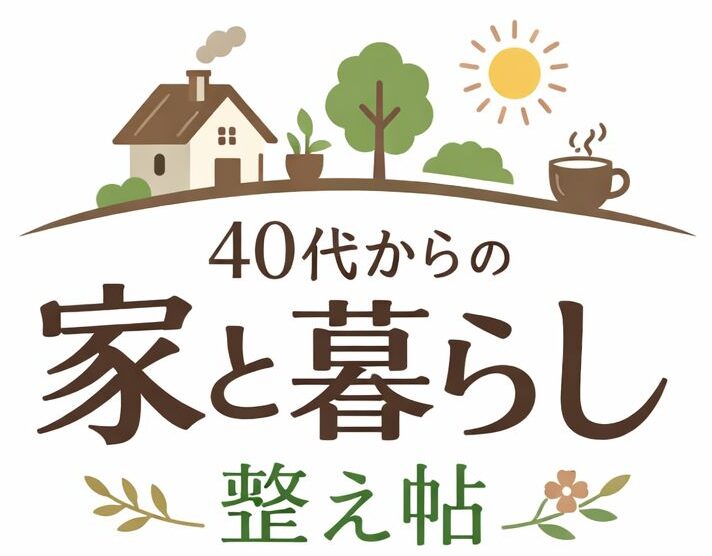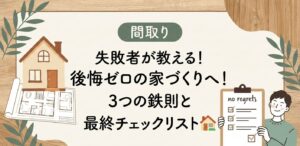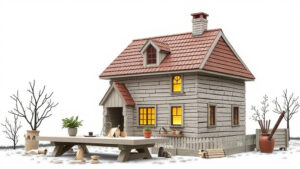はじめに:なぜ「家は人生最大の買い物」で マイホームで後悔 するのか?
私は20歳の時にマイホームを建て、現在築24年になります。親と同居しながら、自分名義で住宅ローンを支払ってきました。
「家は人生最大の買い物」と言われますが、それは本当にその通りでした。若い頃に「マイホームを持ちたい!」という勢いと憧れだけで突っ走った結果、残念ながら今でも「あの時、もう少し深く考えていれば…」「この知識さえあれば…」と マイホームで後悔することが山ほどあります。
特に、インターネットで情報収集が今ほど容易ではなかった時代、私はたった1社だけの提案を鵜呑みにし、将来のことは全く考えないまま契約してしまいました。これが マイホームで後悔 した最大の原因です。
これから家を建てる方、買う方には、私と同じ マイホームで後悔 をしてほしくありません。後悔の8割は「建てる前の準備」で決まります。
この記事では、「 マイホームで後悔 」を徹底的に減らすために、私が築24年の経験から厳選した10のチェックポイントと、具体的な後悔しないための行動リストをご紹介します。この情報が、あなたの「納得できる家づくり」の羅針盤となることを願っています。
【PR】後悔しない間取りづくりをするなら、まずは複数の間取り提案を比較するのがおすすめです。
タウンライフ家づくりなら、あなたの希望に合わせた 間取り・見積り・資金計画を 一度でまとめて受け取れます。すべて無料で依頼できます。
※90秒入力で完了。複数社の間取り提案が届くため、失敗しない家づくりに役立ちます。
✅ マイホームで後悔 を 減らすための必見チェックリスト10項目
家づくりは、夢や理想だけでなく、徹底的なリサーチと現実的なシミュレーションが必要です。特に以下の10項目は、住み始めてから「どうにもならない後悔」に直結します。
1.複数社の比較検討で後悔を未然に防ぐ
【後悔の最大の要因:情報不足】 私が最も後悔しているのが、この点です。たった1社だけの提案で舞い上がってしまい、即決しました。しかしながら、家を建てた後に友人や知人の話を聞くと、「もっと高性能で、もっと使いやすい間取りで、価格も安かったかも」という疑問が消えません。
- 1社だけで決める危険性: 建築費の相場観が麻痺し、業者の営業トークを鵜呑みにしやすくなります。価格だけでなく、断熱性や気密性の技術レベルも比較検討できません。
- 理想的な比較方法: 最低でも3社以上の間取りプランと見積もりを比較しましょう。各社の得意とする工法、デザイン、価格帯、そして担当者の熱意と専門性、アフターフォロー体制を客観的に見極めることが、 後悔 しないための第一歩です。
2. 10年・20年後のライフスタイルも想像したか?
【長期的な視野の重要性】 住宅ローンは通常30年以上です。家づくりはどうしても「今の生活」に焦点を当てがちですが、家族構成や年齢に伴い生活は変化します。将来を見通せない間取りは、大きな後悔につながります。
- 子育てと巣立ち: 子供の成長と巣立ちを想定し、将来的に壁を取り払える間取りや、子供部屋を趣味の部屋や収納に転用できる柔軟性のある設計が求められます。
- 介護と老後: 親の介護や自分たちの老後を視野に入れましょう。バリアフリー設計(段差の解消、手すりの設置スペース)や、主要な生活空間を1階に集約する平屋ライクな動線を検討することが、後悔を防ぎます。
3. 立地は将来的に便利か?(不動産価値の視点)
【後悔の現実:生活の質と資産価値】 立地は後から変更できません。さらに生活の利便性だけでなく、災害リスクや将来の不動産価値にも直結します。
- 日々の生活の質: 通勤・通学時間、最寄りのスーパーや病院までの距離を確認。これらは日々のストレスに直結します。
- 災害リスク: 自治体のハザードマップで、洪水や土砂災害のリスクを必ずチェックしましょう。リスクの高い場所は、保険料が高くなるだけでなく、心理的な不安の原因にもなります。
- 地域の将来性: 地域の都市計画にも目を向け、将来的に不動産価値が維持しやすいかを確認しましょう。
4. 住宅ローンの返済計画にゆとりがあるか?
【最も避けたい後悔:生活の破綻】 「借りられる額」と「無理なく返せる額」は全く違います。無理なローン計画は、日々の生活の質を下げるだけでなく、最悪の場合、家を手放すことになりかねません。この経済的な後悔は最も深刻です。
- 理想の返済額: 住宅ローンの年間返済額は、年収の20〜25%以内に抑えるのが理想です。
- ボーナス返済の罠: ボーナスは不安定な収入源です。ボーナス返済に頼りすぎず、日常の給与だけで無理なく返済できる計画を立てましょう。
- 教育費・老後資金: ローン返済以外にも、子供の教育費や自分たちの老後資金の積み立てを忘れずに計画に組み込み、総合的なキャッシュフローをシミュレーションしましょう。

5. 固定資産税・火災保険などの維持費を把握しているか?
【盲点となる後悔:隠れたコスト】 住宅取得時の費用ばかりに目が行きがちですが、家には「ランニングコスト」が常にかかります。
- 固定資産税: 新築から数年間の軽減措置が終わると、負担が増します。地域の税率や建物の評価額によって大きく変動します。
- 火災保険・地震保険: 保険料は、建物の構造や地域の災害リスク、そして保険会社によって大きく差が出ます。必ず複数社を比較し、地域のリスクに応じた適切な保障を最安値で手に入れましょう。
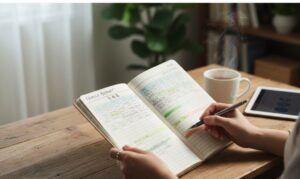
6. 断熱性・気密性・通風は十分か?(快適性と光熱費)
【住んでから気づく後悔:冬の寒さと電気代】 家の「性能」は、快適性と光熱費に直結します。低性能な家は、冬の寒さや夏の暑さ、そして高額な電気代という後悔を毎日もたらします。
- 断熱性・気密性(Q値・C値): 高性能な家は、熱が逃げにくく(断熱性)、隙間が少ない(気密性)ため、エアコンの使用頻度が激減し、光熱費を大きく節約できます。
- 通風(風通し): 間取りを考える際、窓の配置や大きさで風の通り道を意識しましょう。自然の風を効果的に活用することで、夏のエアコン使用頻度を減らし、湿気やカビを防ぐためにも重要です。

7. 収納スペースは十分か?(将来荷物が増える現実)
【片付かない後悔:散らかるリビング】 家を建てる際、荷物は最小限かもしれませんが、生活年数とともに荷物は必ず増えます。特に、日常的に使わないものをしまえる場所がないと、リビングや居室が散らかり、生活満足度の低下につながります。
- 「とりあえず収納」の場所: 季節家電、レジャー用品、子供の作品、書類など、日常的には使わないけれど必要なモノをしまえる「広めの納戸」や「屋根裏収納」を計画しましょう。
- 必要な場所への配置: 玄関に外で使うものをしまう収納、キッチンに食品庫(パントリー)など、使う場所に収納がある計画が、散らからない家への秘訣です。
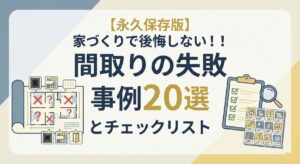
8. 外壁・屋根などのメンテナンス計画を立てたか?
【最も高額な後悔:予想外の出費】 私が築24年目で直面した最も大きな出費が、外壁塗装と屋根の修繕です。この「メンテナンス費用の見積もり不足」は、 マイホームで後悔 したことの中でも、特に家計に大きな打撃を与えました。
私の現実:築24年目で外壁塗装に180万円かかりました。
- 周期と費用: 外壁塗装は10〜15年、屋根の修繕は20〜30年が目安です。数百万円単位の出費は避けられません。
- 長期修繕計画: 30年先までのメンテナンス費用を概算し、毎月いくら積み立てるべきかをシミュレーションしておきましょう。例えば、300万円の修繕費に備えるなら、30年で割って、毎月約8,333円を積み立てる計算になります。
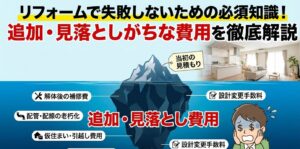
9. 信頼できる業者と出会えているか?
【最も質の悪い後悔:欠陥やトラブル】 どんなに良いプランでも、それを実行する業者が信頼できなければ意味がありません。業者選びの失敗は、欠陥住宅や高額な追加費用という最悪の後悔につながります。
- 「相見積もり」の重要性: 建築時だけでなく、外壁塗装やリフォーム時にも、必ず複数社から見積もりを取り、適正価格と施工内容を比較しましょう。
- 実績と評判: 過去の施工事例、アフターフォロー体制、地域での評判、そして倒産リスクなども含めて、徹底的に調べましょう。
10. 「家を建てたい理由」は明確か?
【精神的な後悔:迷走する家づくり】 家づくりを始める前に、「なぜ家が欲しいのか?」という根本的な問いに向き合いましょう。この「軸のブレ」は、途中で設計変更を繰り返したり、完成後に「なんか違う」という後悔を生んだりします。
- 「自分の軸」を持つ: 「家族との時間を大切にしたいからリビングを広く」「趣味の道具を収納したいから土間収納を」など、「自分たちの価値観」に基づいた明確な理由が必要です。
- ブレない軸: 軸が明確であれば、住宅会社からの提案や、家族間での意見の食い違いが生じた際に、後悔しない判断基準を持つことができます。
🔍 私が実際に マイホームで後悔 したこと:具体的な失敗談
私の経験から、上記のチェックリストがなぜ重要なのかを補強する、具体的な マイホームでの後悔を3つご紹介します。
1. 情報不足のまま1社だけで契約してしまったこと
当時は「大手だから安心」「担当者が熱心だった」という感情的な理由だけで、他の住宅会社と比較検討することなく契約しました。結果として、断熱性能の低さや水回りの設備グレードなど、他社ならもっと良い選択肢があった可能性を、ずっと引きずっています。「手間を惜しまず、情報収集と複数比較をすべきだった」という後悔は、今でも残っています。
2. 親と暮らすことだけを想定した間取り設計
親との同居を前提とした間取りにしたのですが、親が亡くなった後、その空間がデッドスペース化してしまいました。将来的に子供世帯が住む可能性や、賃貸に出す可能性など、「家族構成が変わる未来」への柔軟性が全くありませんでした。住まい手の変化を許容できる「可変性のある間取り」にすれば良かったと後悔しています。
3. 外壁塗装など、将来のメンテナンス費用を想定していなかったこと
これが最も家計に響いた後悔です。ローン返済の計画ばかりに気を取られ、15年ごとの外壁塗装や30年ごとの水回り設備交換といった、「避けられない高額な出費」を全く考慮に入れていませんでした。
- 貯蓄不足: 外壁塗装の180万円を、慌てて貯蓄から捻出することになり、生活防衛資金を大きく切り崩しました。
- 教訓: 建築費の1〜2割は、将来の修繕費としてローン完済まで別枠で積み立てる意識が必要です
・1社だけで契約してしまったこと
・親と暮らすことだけを想定した間取り設計
・外壁塗装など、将来のメンテナンス費用を想定していなかったこと
このような後悔を経て、ようやく「今ならこうするのに…」という知識と視点を持てました。
📌 マイホームで後悔 しないための行動リスト(PRリンクあり)
マイホームで後悔 を減らすためには、情報収集と徹底的な比較検討が不可欠です。これらのサービスを活用し、賢い準備を進めましょう。
🏡【無料】複数の住宅会社に間取り・見積もり相談する
たった90秒の入力で、全国の厳選住宅会社から間取りプランと資金計画を無料で受け取れます。
土地なし・平屋・二世帯住宅にも対応。迷っている方もOK。
<PR>
🔥 火災保険の見直しで保険料がグッと下がる!
最大16社・53商品を比較でき、同じ保障内容でも数万円差が出ることも。
<PR>
🎨 外壁塗装の見積もり比較で数十万円安くなることも!
厳選された優良業者600社以上。中立で比較可能・見積もり依頼数に上限なし。
💡 【深掘り解説】マイホームで後悔 を生まないための具体的な資金計画
前述の通り、後悔する最大の理由の一つは、資金計画の甘さです。具体的に、経済的な後悔を避けるために考慮すべきポイントを深掘りします。
1. 住宅ローンは「収入合算」で借りすぎない
夫婦共働きの場合、収入を合算して借り入れ可能額を増やすことができます。これはあくまで「借りられる額」であり、「無理なく返せる額」ではありません。
- リスクヘッジ: どちらか一方が病気や転職で収入が途絶える可能性を考慮し、主たる収入源の方の給与だけで返済が可能な水準に抑えるのが理想です。
- 出産・育児期間の収入減: この期間も返済に困らないよう、当初の返済額を低めに設定しましょう。
2. 頭金は貯蓄の2割〜3割を目安に
「頭金が多いほど良い」とされますが、その一方で、手元の現金がゼロになるのは非常に危険です。
- 手元に残すべき資金: 少なくとも生活費の半年分〜1年分は、緊急予備資金として必ず残しましょう。この資金は、病気、失業、急な修繕費(例:給湯器の故障)などに備えるためのものです。
- 諸費用の考慮: 仲介手数料、登記費用、火災保険料など、住宅価格の1割程度の諸費用は現金で必要になることを忘れてはいけません。
3. 「固定金利」と「変動金利」のリスク許容度を把握する
金利タイプ選びも、将来の後悔を大きく左右します。
- 変動金利: 当初の金利は低いですが、将来的な金利上昇リスクがあります。ただし、このリスクを許容できるのは、「金利が上昇しても繰り上げ返済できる貯蓄力がある」家庭に限られます。
- 固定金利: 金利は高めですが、将来の返済額が確定するため、ライフプランが立てやすいメリットがあります。特に、資金計画を確実にしたい方におすすめです。
まとめ:家は「建てる前の準備」で後悔の8割が決まる
私は築24年の間に、たくさんの家づくりで後悔を経験しました。
家づくりは、人生において最も高額で、最も長い時間を過ごす場所を決める一大イベントです。
後悔の8割は、着工してからではなく、「建てる前の情報収集と準備」で決まります。
どうか、この記事を読んでくださったあなたが、納得できる家づくり、安心できる暮らし🍀を手にできますように。