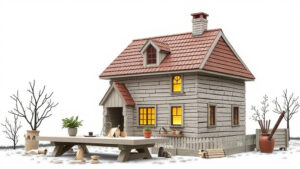「家を買うなら、今なのか?」「後悔しない 住宅購入 って、どうすればいい?」
そう考えている人は少なくありません。
私自身、20歳のときに住宅ローンを組み、親と同居する形で家を建てました。
当時は「家がある=安心」と思っていましたが、実際に暮らし始めてから見えてきた現実は、想像以上にシビアなものでした。
築24年を迎えた今だからこそ伝えたいのは、 住宅購入 は“ゴール”ではなく、“スタート”だということです。ローン返済だけでなく、維持費やリフォーム費用といったランニングコストが、今後数十年にわたって家計に重くのしかかります。
この記事では、私が経験から学んだ「後悔しない住宅購入のための3つの行動」を、リアルな体験を交えてお話しします。
🏠【後悔と学び1】たった1社に決めたことの代償!住宅会社は最低3社以上比較すべき
私は建築を依頼する際、友人から紹介された1社だけに相談し、そのまま契約してしまいました。
今振り返ると、これが最大の失敗だったと感じています。なぜなら、その会社が提案してくれたプランや価格が市場で見て適正だったのか、他の選択肢ならもっと理想の家に近づけたのではないか、という疑問に答えが出ないからです。
家づくりにおいて、情報比較を怠ることは、損をする確率を高める行為にほかなりません。
住宅会社を「比較しない」ことで生まれる3つの損失
| 損失の種類 | 具体的なリスクと金額 |
| 機会損失 | 他社ならもっと高性能、あるいはデザイン性の高い家を同じ予算で建てられたかもしれない。 |
| 価格損失 | 相見積もりによる価格交渉の余地を失い、数十万〜数百万円、割高な金額で契約している可能性がある。 |
| 知識損失 | 複数の会社の話を聞くことで得られる最新の技術や相場観が身につかず、提案内容を鵜呑みにしてしまいました。 |
ハウスメーカー(HM) vs 地元工務店:どっちが本当にお得?
「どこに頼むか」で、価格、品質、自由度が大きく変わります。私は工務店に依頼しましたが、それぞれにメリット・デメリットがあり、「お得」の定義は人それぞれです。
| 会社の種類 | メリット | デメリット |
| ハウスメーカー(HM) | 品質が均一で安心、工期が短い、保証が充実している、最新技術に対応している。 | 広告宣伝費などが含まれるため価格が高い傾向、自由度が低い(規格内設計が多い)。 |
| 地元工務店 | 建築費が安い傾向(広告費などが少ない)、自由度が高い、地域特性に詳しい。 | 会社ごとの技術力に差がある、情報収集・融資手続きなどを自分で進める必要がある場合がある、倒産リスクの検討も必要。 |
【学びの応用】 まずはハウスメーカーと地元工務店をバランスよく資料請求し、それぞれの価格帯と得意な工法(例:高気密高断熱、耐震性)を把握することから始めるべきでした。
こちら👇の記事も参考にしてください
【2025年最新版】ハウスメーカーと地元工務店どっちがいい?後悔しない家づくりの選び方
💡 最初の一歩を効率化する【参考ツール】
✅【PR】タウンライフ家づくり:手間なく比較するなら必須のツール
比較を始める際、一社ずつ回るのは非効率です。複数の会社から、あなたの土地と予算に合わせた具体的な間取りプランと概算見積もりをまとめて入手できるサービスを活用すれば、市場の適正価格を最短で把握できます。
「タウンライフ家づくり」は、あなたの要望に合った複数の住宅会社から無料で間取りプランと見積もりをまとめて取り寄せることができます。手間なく具体的な比較検討を進めるためのツールとして、活用を検討してみてください。
「一括資料請求」と聞くと構えてしまいがちですが、タウンライフの強みは、単なるカタログ送付にとどまらない「オーダーメイドの提案」にあります。
- 手間なく比較: スマホでたった3分の入力。希望の土地情報や間取りのイメージを伝えるだけでOK。
- プランを比較: 複数の会社が、あなたの予算と敷地に合わせた間取りプランと概算見積もりを作成・提案してくれます。
- 営業を抑制: 資料請求時に「しつこい電話は不要」とチェックする項目もあり、営業のストレスを最小限に抑えられます。
最低3社以上から具体的に比較できるプランを手に入れることで、初めて市場の適正価格と自分の理想に一番近い会社が見えてきます。土地なしOK・平屋プランあり・間取り提案無料」など、自分に合った条件で選べます。
🏠【後悔と学び2】10年後、20年後の変化を無視した間取りは必ず後悔する
私は親との同居前提で家を建てたため、「とにかく部屋数を確保」することに注力しました。しかし、24年が経過し、家族の状況が変わった今、「もっと間取りにゆとりが欲しかった」「介護の導線を考えていなかった」と後悔しています。
住宅の寿命は数十年に及びます。その間に、家族構成、働き方、健康状態は必ず変化します。家づくりは、今の家族だけでなく、将来の家族構成と生活をデザインする作業です。
ライフステージ別で考える「失敗しない間取り設計」
| ライフステージ | 変化のポイント | 後悔しないための間取りアイデア |
| 子育て期 | 子ども部屋の確保、荷物の増加、家事負担の増加。 | 可変性のある子ども部屋(最初は広い一部屋→将来間仕切り)、リビングを通る階段(コミュニケーション維持)。 |
| 親との同居・介護 | プライバシーの確保、身体機能の低下への対応。 | 1階に親の寝室とトイレを確保(バリアフリー対応)、音が届きにくい世帯間分離の工夫。 |
| 夫婦二人(老後) | 階段の上り下り、掃除・メンテナンスの負担軽減。 | 平屋的な暮らしができるよう主寝室を1階に配置、広い家よりもコンパクトで動きやすい動線を優先。 |
| 在宅ワーク | 個人の集中スペースの確保、生活音の遮断。 | 書斎のような集中できる個室を設けるか、寝室やリビングの隅にヌック(こもり空間)を設ける。 |
【学びの応用】 間取りを考える際、「今」の不満解消だけでなく、「20年後の自分たちがどう暮らしたいか」を具体的にシミュレーションしてください。
特に、高齢になった際の「寝室とトイレの配置」は、夜間の安全性を左右する重要な要素です。もし、将来のイメージが湧かない場合は、専門家による無料相談サービスを活用して、第三者の視点を取り入れるのが賢明です。

🏠【後悔と学び3】住宅ローンの陰に隠れた「維持費」の恐ろしさ
住宅購入で誰もが住宅ローンの返済額ばかりに目が行きがちです。私もそうでした。しかし、住み始めて24年が経ち、本当に痛感したのは、「家を持つ=維持費との長い付き合いが始まる」ということ。
ランニングコストを具体的に計算していなかった結果、突然の高額出費に慌てることになりました。
戸建ての年間ランニングコストの相場
戸建ての年間ランニングコストは平均で30万円~50万円ほど(月額2.5万円~4万円)が相場とされています。この費用には、主に以下の項目が含まれます。
| 費用項目 | 支出サイクルと私の経験 | 対策のポイント |
| 固定資産税 | 年に1回(私の場合は年7万円ほど) | 減税措置の確認。都市計画税の負担も考慮する。 |
| 火災・地震保険料 | 1年~10年ごと | 補償内容の重複を避ける、複数社比較で保険料を節約する。 |
| 光熱費(水道・電気・ガス) | 毎月 | 高断熱・高気密の家を選ぶことが、長期的な節約に最も効く。 |
| 修繕・リフォーム費 | 10年〜20年ごと | 毎月積立てておくこと。外壁塗装は特に高額(経験では180万円)。 |
特に注意すべき「高額な維持費」:保険とリフォーム
1. 火災保険・地震保険
住宅ローンは組めても、火災保険の費用は忘れがちです。しかし、2022年10月の改定で保険料が値上がりした今、保険の見直しと節約は必須です。
- 保険期間: 以前は最長30年でしたが、現在は最長5年に短縮されました。短い期間で再契約が必要になり、総支払額が上がる可能性もあります。
- 節約のコツ: 不要な補償を外す、水害リスクがない地域なら水災補償を外す、必ず複数社を比較する。
✅【PR】火災保険を比較して節約するなら 「住宅本舗の火災保険一括見積もりサービス」
「住宅本舗の火災保険」は、複数社の保険を比較検討できるサービスです。
- 複数社比較: 火災保険料や補償内容を比較することで、年間数万円単位で保険料を節約できる可能性が高まります。
- 最適なプラン: 自分の家や地域のリスクに合わせた最適な補償内容(水災不要など)をプロに相談しながら選択できます。
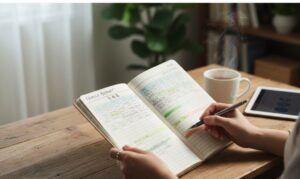
2. 外壁塗装・屋根リフォーム
私が築24年で経験した180万円の外壁塗装は、計画性のない大きな出費となりました。戸建ての場合、約10年〜15年に一度、大規模な修繕(外壁・屋根・水回りなど)が必要になります。
- 修繕費用積立の目安: 30年間で300万円〜600万円程度の修繕費がかかる計算です。月々1〜2万円を意識的に積み立てる必要があります。
- 失敗を避けるには: 外壁塗装は相場が不明確なため、悪徳業者の高額見積もりに引っかかりやすい分野です。必ず複数社から見積もりを取り、比較検討することが重要です。
✅【PR】外壁塗装・屋根リフォームの相場を確認するなら 👉 タウンライフ外壁塗装
タウンライフが提供する「タウンライフ外壁塗装」は、外壁塗装の相場を知るのに役立つサービスです。
- 相場を把握: 外壁塗装の概算相場を知ることで、契約時の見積もり額の妥当性を判断できるようになります。
- 業者比較: 複数社から比較することで、品質の良い業者を適正価格で見つけ出すことができます。

🏠徹底解説!後悔しない家づくりのための「資金計画」全体像
家づくりで後悔しないためには、「住宅価格(イニシャルコスト)」と「維持費(ランニングコスト)」の両方を含めた「生涯コスト」で考えることが非常に重要です。
ステップ1:総予算を決める
まずは、住宅価格、諸費用(税金・保険・登記費用など)、引越し費用など、すべてを合計した**「総予算」**を決めましょう。
- 総予算の決め方: 「借りられる額」ではなく、「無理なく返せる額」で決めます。維持費や教育費など、将来の出費も考慮し、毎月の返済額の上限をシミュレーションしてください。
- 諸費用の相場: 建築費の**約10%〜15%**が目安です。この費用はローンに組み込めない場合もあるため、自己資金で用意できるか確認が必要です。
ステップ2:住宅ローン選びで失敗しないための視点
20歳でローンを組んだ経験から言えば、「金利タイプ選び」は将来の家計を大きく左右します。
| 金利タイプ | 特徴 | 向いている人 |
| 変動金利 | 金利が低く、当初の返済額が少ない。将来金利上昇のリスクがある。 | 金利上昇リスクを許容できる人、数年後に繰り上げ返済の予定がある人。 |
| 固定金利 | 借入期間中、金利が変わらない。返済計画が立てやすい。 | リスクを避けたい人、長期にわたって安心したい人、家計に余裕を持たせたい人。 |
ステップ3:家計を守る「税金優遇制度」の活用
「知っているかどうか」で数百万円の差が生まれるのが、国の優遇制度です。
- 住宅ローン控除: 年末のローン残高に応じて所得税・住民税が控除される制度です。利用条件や控除額は最新の情報を必ず確認してください。
- その他の補助金: 省エネ性能の高い住宅を建てることで受けられる補助金制度(例:地域型住宅グリーン化事業など)は、初期費用を大きく抑えるチャンスです。

🏠まとめ:家は「建てる前の準備」で満足度が100%変わる
マイホーム取得は、人生で最も高額な買い物です。だからこそ、「情報を知らなかっただけで損をしていたかもしれない」という私のような後悔を、あなたにはしてほしくありません。
私が経験を通して得た教訓は、極めてシンプルです。
後悔しない家づくりのための3つの行動
- ✅ 比較の徹底: 複数の会社に相談・比較し、市場の適正価格とプランを把握する。
- ✅ 未来の設計: 10年後、20年後の家族の暮らし方を想像し、可変性や介護も視野に入れた間取りにする。
- ✅ 維持費の計算: ローン返済だけでなく、維持費・リフォーム費用も具体的に考慮した資金計画を立てる。
家を建てて終わりではありません。家を建ててから、本当の暮らしが始まります。
しっかりと情報を集め、納得できるパートナーと計画を立てることで、きっと、生涯にわたる安心と快適を提供してくれることでしょう。
あなたの家づくりが、後悔のない素晴らしいものになるよう、心から願っています。
🌸関連記事🌸